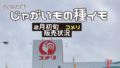家庭菜園だからこそ、酸度の計測は大事!計測方法からおすすめの計測機器まで紹介いたします!
なんで土壌酸度を図る必要があるの?
日本の土壌は酸性に傾きやすく、野菜により、生育に適したpHが異なります。適正pHから外れた土壌で植物の栽培を行うと、植物が養分を吸収しにくくなり、様々な欠乏症の症状が現れ、植物が健全に育ちません。(養分を吸収できなくなります)
野菜の栽培マニュアルを見ると、常に「石灰を施す」と書かれていますが、施しすぎて、土壌がアルカリ性に傾くのは避けなければなりません。
家庭菜園で酸度計まで購入して・・・
という気持ちもわからなくはないですが、始めは培養土を購入し、ただプランターに入れるだけだった土も、収穫を重ねる度に土づくりを行っていく中、現在、土がどのような状態になっているのか?わからなくなっている人も多いのではないかと思います。
家庭菜園こそ、石灰を施しすぎたり、肥料を与えすぎたりしがちですので、長く土を使い回し、家庭菜園を楽しむのであれば、購入を検討しても良いかなと思います。
土壌が酸性に傾く原因は大きく二つ
- 雨水により酸性に傾く
- 未熟な有機物により酸性に傾く
雨は大気中の二酸化炭素や汚染物質などの酸が含まれており、雨水のpHは5.7の弱酸性といわれています。
未熟な有機物は有機物が分解する際に酢酸や酪酸、ギ酸などの有機物を生成する為、土壌が一時的に酸性化します。
作物により、生育に適した土壌pHが異なります
| 区分 | pH | 適した野菜 |
| 酸性 | 5.0~5.5 | ジャガイモ |
| 弱酸性 | 5.5~6.0 | パセリ、サトイモ、とうもろこし、大根 |
| 微酸性 | 6.0~6.5 | トマト、ナス、キュウリ、人参、キャベツ、レタス |
| 中性 | 7.0 | ほうれん草、玉ねぎ、ゴボウ、アスパラガス |
多くの野菜は上記表の黄色い部分。微酸性を好みます。これから外れるものの方が特殊なので、外れる方の野菜を覚えておき、栽培する際は注意をしましょう。(ジャガイモ、ほうれん草等)
土壌酸度の測定方法
いくつかありますので以下に記載はしますが、理想は「デジタル式でECまで測定できるもの」ですが非常に高価です。
週末のお手軽家庭菜園では。。ちょっと購入をためらいます。
いろいろな農業書に土づくりは重要だと書かれ、「土づくりで野菜作りのすべてが決まる!」「苦土石灰を施せ」「元肥を入れろ」といわれますし、肥料が多い方が野菜が大きく育つという先入観から、家庭菜園では多肥になりがちですので、酸度・EC計はどちらも必要とは思います。
ただ・・・どちらも計測できる状況を整えると、出費が半端ない。
肥料は元肥を少な目にして、追肥等で植物の様子をうかがいながら調整はできますが、pHはそうもいきませんので、酸度計、EC計どちらを優先させるべきかというと、酸度計かなと思います。
土壌酸度計の種類
●アナログ式
電池は不要で、センサーを土に挿すと土壌酸度計は土壌中の水素イオンによって電流が流れ、計測されます。
アナログ式のおすすめは下記商品です↓少々高価ではありますが、他の商品がほとんど0.5刻みの表示しかできない中、これは0.2刻みで表示がされます。
Amazonのおすすめにもなっており、酸度計を買うのであれば、0.2刻みの計測ができるこれが良いかと思います。他のデジタルのものもお手頃価格のものは、大概が0.5刻みとなっていますので、それらと比較しても、これが一番良さそうです。
●デジタル式の酸度計
デジタル式は電池が必要となります。アナログ式より多機能で、地温や水分量を計れるものに加え、EC値を図ることができるものがありますが、ECまで測定できるものはかなり高価です。ECが測定できると土壌の肥料濃度が計測できますので、肥料の量の調整にも役立ちますが。。。
下記はデジタルの土壌酸度計の中でAmazonベストセラー1位の商品です↓
価格的にも手ごろで、pH以外にも土壌温度、水分、塩分、育成環境照度の簡易測定ができますが、肝心のpHは0.5刻みです。
レビューでは正確だという評価がある一方、不正確という評価もあり、正確性については疑問が残ります。ただ、同価格帯の商品の中では一番信頼できそうな商品です。
酸度計を使った酸度計測時の注意点
- 計測する土壌を水でしっかり湿らせる
- 測定する部分に土が密着するよう、土壌を踏み固める
- 計測は複数個所行い、平均値をとる
- 堆肥や石灰を施した際は2W以上休ませてから計測する
EC(Electrical Conductivity)とは、電気伝導度のことで、土壌中の残留養分や塩分濃度を知るための指標です。単位はミリジーメンス(mS/cm)またはデシジーメンス(dS/m)です。EC値が高いほど養分量が多い。適正値は0.6~1.0とされています。
とても家庭菜園レベルでは手を出せない価格です、酸度計と合わせて買うと「万」に近い出費になります。
●酸度測定試薬を用いた計測
こちらは数値ではなく、土壌を水に入れ、上澄み液を取り、試薬やpH試験紙の色の変化により、酸性、中性、アルカリ性を見るものです。だいぶ大雑把な計測になります。
上澄み液を作って試験するという面倒さはありますが、アナログだからこその安心感はあります。価格的にも大変手ごろ。大体のイメージをつかむだけであればこれでも十分こと足りると思います。
まずはこれを試してみて、やっぱり面倒と思うなら、計測器を購入するということでもよいかと思います。
①土20g:水50gの割合で水に溶き、土を拡販します。
②しばらく静置し、土を沈殿させ上澄み液を利用し計測します。
土壌酸度の調整方法
pHを上げたい場合
- 石灰を施す
Phを下げたい場合
- 硫安や過リン酸石灰などを施す
- ピートモスを混ぜ込む(土壌に対して20~30%でpH0.2~1.0下がる)
pHを下げる方は比較的難しいとされています。通常、土壌が勝手にアルカリ性に傾くことはないので、石灰を施す際にはアルカリに傾きすぎないように注意することが重要です。
結論
測定器もピンキリで、測定数字の信ぴょう性を調べようにも、なかなか難しい。それなりのお金を出して誤差範囲の少ないものを購入するか?手間はかかるけど試験紙等の古典的な測定をするのか?のどちらかかなと思います。
※ブログランキングに参加しています。下記バナーをクリックして応援よろしくお願いいたします!